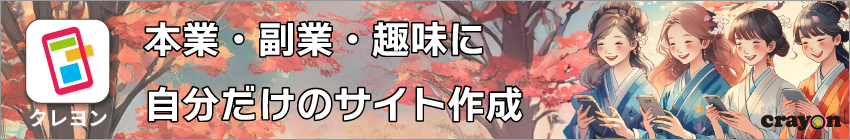東洋医学
東洋医学では人体を構成する要素である
「気」「血」「津液」「精」のバランスの乱れで不調が起こると考えます。
それぞれが不足しているのか、余って停滞しているのか、なぜ足りないのか、なぜ停滞してしまっているのか、またどの臓腑が関係しているのかを見極めていく必要があります。
それを踏まえて、鍼灸治療では関連する経絡のツボを刺激することで、気血や臓腑の変調を整え、働きを正常に戻し、身体の隅々まで血が巡る元気な身体へと導きます。
アーユルヴェーダ
インド・スリランカの伝統医学であるアーユルヴェーダ。
アーユルヴェーダでは、ドーシャというエネルギーのバランスが乱れることで消化力に異常をきたし、「アーマ」(未消化物・毒素)が体内に蓄積することで病気になると考えています。
身体には、栄養素やエネルギー・老廃物を運ぶために全身に張り巡らされた管である「スロータス」があると考えられており、重くべっとりした粘着質なアーマは、このスロータスに溜まり蓄積します。
アーマが溜まり、スロータスが詰まると、必要な栄養素やエネルギーも全身に行き渡りません。老廃物も排泄されずどんどん溜まる一方です。
またアーマには精神的なストレスで消化されずに残るメンタルアーマも存在します。
モヤモヤした気持ちや、後悔などもアーマとなって身体に蓄積してしまうのです。
「油の汚れは油で落とす」
というアーユルヴェーダの考えをもとに、オイルマッサージでスロータスを柔らかくし広げ、循環を良くして身体も心もスッキリとデトックスしていくことが元気への第一歩となります。
東洋医学とアーユルヴェーダの共通点
5000年以上前から存在するアーユルヴェーダが発祥となり、中国へ伝わり現代の東洋医学に発展していったと言われています。
共通点も非常に多く、東洋医学でいう「ツボ」というものは、アーユルヴェーダでは「マルマ」といいます。
これらが身体に位置する場所もお互いとても似ています。
他にも東洋医学では「清気」、アーユルヴェーダでは「プラーナ」を呼吸によって取り入れてエネルギーを生み出すというところ。
呼吸法も様々伝えられています。
そしてどちらも特に大切と考えているのが消化吸収の力ではないかと思います。
気・血・津液・精は、生まれた時に両親から受け継ぐものや呼吸から取り入れるもの、そして脾胃が飲食物を消化吸収することで生成されます。
アーユルヴェーダでは「アグニ」(消化の火)の力が大切と考えていて、主に食べ物の消化と体内の代謝の働きをしています。
ドーシャのバランスがよいとアグニが正しく働きます。アーマも常に消化され身体に溜まらず、心も身体も健やかに過ごせるのです。
東洋医学でもアーユルヴェーダでも、元気な身体をつくるのは自分で消化吸収して取り込み、作り出し、巡らせる力があってこそだといえます。